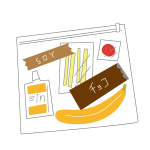着衣泳指導のプール授業 服装や持ち物 講習の流れは?

皆さんは服を着たまま泳ぐという経験をしたことがありますか?
子どもの小学校で近年行なわれるようになった着衣水泳の授業があります。
これは本当に子どもたちにぜひ受けさせておきたいと私は常々思っていたのでありがたい指導でした!
その日の服装や持ち物、講習の流れについてお伝えします。
着衣泳の服装は?
うちの子どもたちの小学校では毎年9月、その年最後のプール授業が着衣水泳の特別講習となります。
対象学年は5年生、授業日程はプール納めの日の5、6時間目となっています。
着衣水泳ではいつ起こるかわからない災難に備え、児童全員が水着ではなく普通の服を着て運動靴を履いてプールに入るのです。
そのため次に入る児童がいない、プールが汚れても良い最終授業がこの講習には最適です。
すぐに水を抜いて清掃できる、プール納めの最後の授業が着衣水泳の指導の日になるんですね。
この授業での服装はうちの子ども達の学校の場合、
- 水着
- 長袖のトップス
- 長ズボン
- 運動靴
となります。
水着を下に着て準備し、その上に洗濯してある長袖長ズボンの私服を着ます。
着衣泳の授業の靴は上履きはNG、登下校用に履いていく靴とは別に普段履いているスニーカーを持参して履きます。
特に学校からは言われませんでしたが靴も洗濯済みのものがプールに入るマナー的に良いですよね。
靴を洗うのが間に合わないなら、最低でも靴底の泥は落として持たせるほうが良いと思います。
上履きは教室に戻る際に使うので、上履きでの参加は不可となっていました。
さて、なぜ長袖、長ズボンなのかというと水の抵抗を受けやすく「水の中で服のまま泳ぐことの難しさ」をより深く体験できるためでしょう。
ケガ防止などの理由もあると思いますが、やはり水の抵抗を最大限に体験するには長袖&長ズボンが最適でした。
この理由からか、動きやすく速乾性のある体操服はダメとなっています。
服装は学校により、水着は着ずに下着の上に洋服、半袖可、ジャージ可、女子はスカートも可となっているところもあるそうでさまざまです。
授業が行なわれる前に先生に服装の確認をしてみてくださいね。
「うちの子はおっちょこちょいだから水の怖さをわからせる!」と、親御さんが真夏にもかかわらずジャンパーにジーンズを持たせた子も過去にいたそうです。
厚みのあるコートやジーンズは流木などによるケガは避けやすいですが、素材が水を含みやすく重くなり、水の中では動きづらいものです。
あえてジーンズをはかせた親御さん、立派だと思いました。
着衣泳の持ち物
着衣泳では当日登校した時とは別の服でプールの着衣泳授業を受けます。
つまり服装も持ち物のうちに入ります。
その他の持ち物は以下のようなものでした。
- 水に入る服装の準備(水着、長袖、長ズボンの洋服、運動靴)
- 2リットルのペットボトル(ふた付)
- 替えの靴下や必要な着替え
- バスタオル
- 濡れたものを入れるビニール袋2枚
- プールカード
当日うちの子の学校では必要ありませんでしたが水泳キャップ(帽子)やゴーグルなどが持ち物に入っている学校もあるそうです。
プールカードと普段のプール授業のプールバッグを持って行くのが安心かもしれませんね。
ペットボトルは抱いて背浮きをする時に浮き具として使ったそうです。
着衣泳講習の流れ
着衣泳講習は新鮮な体験という楽しさの中に緊張感があふれた授業となったようです。
小学生が指導員のもとで行なった着衣水泳講習のプログラムは以下のようなものでした。
着衣泳のプログラム
- まずは服を着たままプールに入り、着衣だとどれほど体が重く感じるのかを体験する
- その後歩いたり、体を動かしてみて、服を着た時には水の抵抗がどれほど大きいのかを体験する
- 次に泳げる人は少し泳いでみる(なんとか泳げる子もいますが実際は泳ぐのは危険であると指導があります)
- 水着で泳ぐのと着衣で泳ぐときの違い、体力の消耗を比べてみる
- 服の空気を浮き輪代わりしてに浮かぶ練習
水に浮かぶと洋服に空気が入り膨らむので、その空気を逃がさないように衣服をギュッと持たせて服の空気を浮き輪代わりにします - 一番大切なラッコのような浮き方「背浮き」を学ぶ
- 次にペットボトルを抱いてラッコのようにぷかぷか浮かぶコツをつかむ
- 周りにいる児童は水中の児童に「浮いて待て」と叫び、周囲の人に助けを求める練習をする
下の表にあるような救助用具になりそうなものを投げてどれが水中で良く浮くかまたは役立つか体験します
指導員さんが用意してくれたプールに投げて救助に使えそうなものは以下のようなものです。
- ランドセル
- 段ボール
- クーラーボックス
- ロープや縄とび
- バケツ
- トートバッグ、通勤バッグ
- 木の棒
- レジ袋、ビニール袋
- 長靴
プールの中で、
「助けてー!」「大声出すと苦しくなって溺れるからやめろ!」
「イテッ!誰だオレの頭に長靴投げたのは!」
と騒々しく盛りあがって授業は大成功だったそうです。
着衣泳のプログラムは水の抵抗の中で服のまま動くことや浮いて待つことの大切さ、周りの人ができる救助の方法などを学ぶのがねらいでした。
2時間をフルに使って子どもたちは十分に水の怖さや浮いて待つことの大切さ、助け方を学べたようでした。
着衣泳は小学校だけではない
子どもの通う学校で着衣泳の指導が授業化されているのはとてもラッキーだと思いました。
もし通っていらっしゃる小学校や中学校の授業で着衣水泳プログラムがなければ「地名+着衣泳」などでチェックしてみてください。
講習を主催している団体が近くにある場合があります。
大人でも受講可能なコースがあるはずですので受けたことがないかたはぜひどうぞ。
この機会にぜひ事故に合わないための予備知識を増やしてくださいね。
ご参考になれば幸いです。